プレゼン作成も反復型開発で(^-^)(2)
前回 に引き続き、私のプレゼン作成方法について書きたいと思います。
私が実施している反復型開発は、Unified Process に基づいています。したがって、方向づけ(Inspection) - 推敲(Erabolation) - 作成(Construction) - 移行(Transition) というフェーズがあります。
各フェーズでどれくらい反復しているのか?というと・・・この辺は実に適当であったりします。だいたい
- 方向づけフェーズ: 1 ~ 2 回 (I1, I2)
- 推敲フェーズ: 2 ~ 3 回 (E1, E2, E3)
- 作成フェーズ: 3 ~ 6 回 (C1, C2, C3, C4, C5, C6)
- 移行フェーズ: 1 ~ 2 回 (T1, T2)
こんな感じかなと思います。たかがプレゼン作成にしては反復の回数が多いと感じるかと思いますが、プレゼン作成だから個々の作業自体の期間は短いということと、私の性格から回数は多めになっています。飽きが来なく、さらに途中の方針転換の柔軟性も備えた(私にとっての)理想的なモデルがこれになります(万人にウケルモデルではないと思います・・・)。
ちなみに1回の反復の期間ですが、1日だったり、半日だったり、1時間だったり、30分だったりします(^^) どんなに時間を割いたとしても1回の反復が1日(24時間)を超えることはないですね。
基本的に、プレゼン作成に没頭できるわけでもありませんので、ある程度別のことをしていてもすぐに戻って先に進めることも重要になってくるんですよね。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
方向づけ
ここでは、「何を伝えたいか」「それをどう伝えるか」を決定することを目標にしています。イベントなどの場合は、特に時間制約や他のセッションとの兼ね合いといった大人の事情も加味する必要があるのですが、そのあたりもこの辺で考慮することになります。この時点での PPT (PowerPoint のファイル(正確には pptx ですね。今は) はほとんど白紙にちょこちょこっと文字が書かれているようなものになります。
伝えたいメッセージのスライドとそこへ導く(もしくはあ逆にメッセージとその理由づけ)くらいのものになります。このレベルでは、当然皆様にお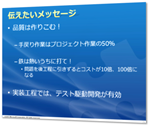 披露目できるしろものにはなっていません。しかし、内部でコンテンツ内容を議論したりする材料にはなりえます。
披露目できるしろものにはなっていません。しかし、内部でコンテンツ内容を議論したりする材料にはなりえます。
「おれはこれを伝えたいんだかぁ~」と叫ぶことはできるわけですね(^^)
※気分が乗ってきている場合には、ここで上述のスライドのみを完成版に近いレベルで作成し終わっていることになります。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
推敲
ここでは、全体のプレゼンストーリーを決定します。作成するにあたって必要となるクリップアートや再利用可能な部品を集めてきたり、製品に関連するセミナーの場合には、製品での動きの検証なども必要に応じて行います。
特にベータ版だったりすると、まだその機能が使えない・・・なんてこともあるので、確認は必要になります。ついでに画面のスクリーンショットなんかもとれるものはここで撮っておきます。
余談ですが、画面スクリーンショットは、基本的 PNG 形式で画像フ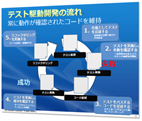 ァイルとして保存していくことにしています。スクリーンキャプチャは OS の機能で行い、画像を加工する必要がある場合は、Paint.NET で行っています。 Power Point 2007 だと、結構いろいろな加工ができるのでそっちで事足りるものはもちろん、それで間に合わせています(本格的なスクリーンショットとその加工は、作成フェーズで行います)。
ァイルとして保存していくことにしています。スクリーンキャプチャは OS の機能で行い、画像を加工する必要がある場合は、Paint.NET で行っています。 Power Point 2007 だと、結構いろいろな加工ができるのでそっちで事足りるものはもちろん、それで間に合わせています(本格的なスクリーンショットとその加工は、作成フェーズで行います)。
この時点では、全体の骨子が固まり、ある程度軸となるスライドが絵付きで作成された段階になります。その他のスライドは文字で書かれていた り、「こんな感じのスライドにする予定」と書かれていたり、作りかけであったりしている段階です。
り、「こんな感じのスライドにする予定」と書かれていたり、作りかけであったりしている段階です。
この時点では、表現方法もある程度形式化しておきます。たとえば、まず説明スライドが文字ベースであり、つぎにイメージスライドがあり、それから・・・といったものです。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
作成
ここで、本格的に「作る」ことを目標にします。基本的に、まず文字情報として、まず完成をさせます。この時点で不運にも、締切がきてしまっても、絵はありませんが実施可能な ppt にはなっているはずです。
実際には、途中で締め切り!!となってしまった場合は、全体のバランスを見て、絵を取るか/文字で統一するかなどを考えることになります(それを考えるのは本来は移行フェーズになります)。
もちろん、途中で締め切りにならないようにタイムマネージメントしているの で、ここまでひどいケースにはなりません。提案活動などだと、特定のお客様に特定の提案をご提示するのが目的になりますし、かつ、急なコンテンツ作成などが日常茶飯事ですから、こういうケースがよくありました。
で、ここまでひどいケースにはなりません。提案活動などだと、特定のお客様に特定の提案をご提示するのが目的になりますし、かつ、急なコンテンツ作成などが日常茶飯事ですから、こういうケースがよくありました。
文字情報だけで、ストーリーが固まったら、詳細についてどういう 表現が一番説明しやすいか、理解していただけるかを個々に考えていきます。基本的な表現方式はたいだい推敲フェーズで固まってはい ますが、作っていきながら変更していくことももちろんあるんですね。
基本的にはプレゼンは、このフェーズで完成をさせます。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
移行
ここでは、最後に提出すること、このプレゼン資料が世の中にだされていくことを考え、手を入れていきます。具体的には、アニメーションや印刷形態に応じた調整(印刷は、 グレースケールか単純白黒かカラーかなど)、誤字脱字の最終チェック、つぶれた文字などがないかのチェックなどに注力します。
グレースケールか単純白黒かカラーかなど)、誤字脱字の最終チェック、つぶれた文字などがないかのチェックなどに注力します。
ここで時間が余っていたりすると、いらぬアニメーションとかが増えて反ってわかりにくいものになってしまうので、注意が必要ですが・・・。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
実際には、個々の作業は、フェーズにかかわらず実施しているところもあります。たとえば、気分が乗っていれば方向付けや推敲フェーズであってもアニメーションまでこしらえてしまっている箇所もあったりします。ただ、全体の流れだけは意識しています。「ここでそんなにディテールにこだわっている場合じゃないよ」と自分を戒める意味でもこれは重要です。
今何をすべきか、全体として何をすべきかを忘れないこと。それに気をつけた結果の解がやっぱり反復型だったという感じでしょうか。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
最後に、実は実は、毎回こんなにまっさらから文字で情報整理して、イメージ図を作成して・・・と手間をかけているわけではありません。再利用を結構考えています。再利用の単位は、プレゼンの一部を切り出したようなものから、1枚のスライド、そしてイメージ図などの部品に至るまで考えています。そんな話を番外編として次回に投稿したいと思います。
余談ですが、プロセス改善も反復して行うべし!なんですよね。プロセス改善のでも「今 E1 だから、・・・」なんて会話したりもします。一般人からすると何を言っているのかわからない暗号チックでいいですよね(^^)
ながさわともはる
Comments
Anonymous
January 28, 2008
PingBack from http://blogs.msdn.com/tomohn/archive/2008/01/28/7276577.aspxAnonymous
February 03, 2008
プレゼン作成も反復型開発で(^-^)(1) プレゼン作成も反復型開発で(^-^)(2) 私のプレゼン作成方法について、書いてきましたが、今回が最終回(番外編)となります。パート2の最後に番外編について触れておきながら、投稿のタイミングを逸していました(というか忘れてました。すみません)。