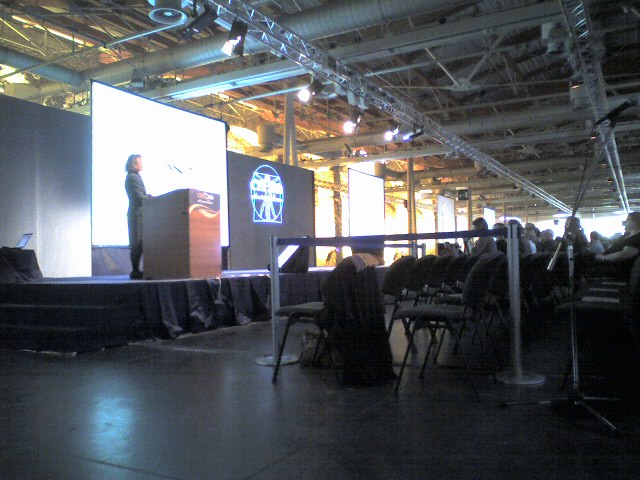CHI 2008 Monday
CHI は「カイ」と読むのですね、月曜日のキーノートを聞いていて初めて知りました。初日にKeith Butler氏が「HCI (こちらのほうがよくつかわれます) じゃ発音できないからね」と言っていたので、CHIってどう読むのかと思っていました...
さて、月曜日はIrene McAra-McWilliam氏による講演(Opening Planary)から始まり、そのあとは各90分の分科会に分かれました。私は以下の3つに出席しました。午後6時半からは出展社主催のパーティもありました。
- Don't Inerrupt Me (Papers/Notes)
- From Usability To User Experience : What has really changed in practice in the last 25 years. (Panel)
- Usability Case Study (Case Studies)
参加登録者は2300名(61カ国)、2000の論文応募があり、通ったのは582とのことでした。毎日朝にはCHI Madnessというその日のセッション(論文発表など)の各人が30秒で自分の発表を紹介するというイベントがあります。SIGGRAPHでは最初の日に論文総まくりのセッションがありますが、これを毎日やっています。
講演で興味深かったのは、「Imagination = Image in Mind」であり、「Creative Imagination」のためには様々な要素Idea(Ways of thinking, imagination, Product), Object(Ways tof making, instanciation, Craft), Self(Ways of Seeing, insight, Interaction), World(Ways of being, identity, Tranformation)を考慮する必要があると指摘していた点でした。「結局センスだよ」などという言葉で終わらせない、重層的な考え方が印象的でした。
分科会セッションの中では、「ユーザビリティからユーザーエクスペリエンスへ」のパネルが最も興味深いものでした。パネリストは以下のとおりです。
- JohnKarat (IBM Research)
- Robin Jellries (Google)
- Gibert Cockton (Guerilla UX?)
- Stepanie Rosenbaum (Tec-Ed Inc)
- Ian MaClelland (Philips)
Ian氏の肩書きの変遷は面白く、1970年代に「Ergonomist」、1986年に「Usability Engineer」、現在は「User Experience Architect」と変遷しているそうです。そして25年の変化を以下のようにまとめて、企業内での価値が向上してきていると指摘しました。
- Usability (Remedial design)→User Experience (Proactive Design)
- Design of artifact → Design Value
- Criteria artifact, operation → Criteria long term value + experience/ aesthetic aspec
- Organization position, Ad hoc, speciallist suport, Post hoc → Organization position, integrated team effort from day#1, particiopate in strategic planning, Competition for "UX ownership"
Stephaie氏は、変化したものとして「acceptance of user research to information design」の延べ、5年前はユーザビリティを企業トップの机上にどうのせるかを議論していたが、現在はもう当たり前になったと指摘しました。彼我の差を感じましたが、質問の中では、現在でもデザイナのValueが認められないという意見もありました。
講演とパーティ(室内楽付き)の写真を掲載します。